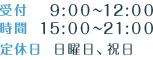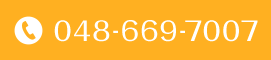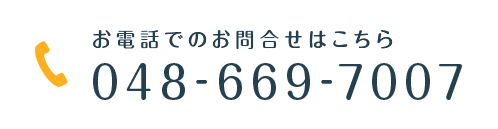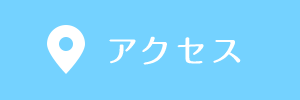2015.07.25更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
暑い日が続きますね。しかし、この暑さを逆手にプールで水中運動なんてどうですか?
○水中運動のすすめ
水中は、浮力・水圧といった力を受けることになります。この中で運動することにより、日常生活とは違う環境・違う動きにより鍛えることができるんです。水と空気の密度を比べると水の方が大きく、水中と陸上とで同じ姿勢・同じ速度で移動しても、陸上に比べ水中では約800倍の抵抗を受けると言われています。また水には、空気の20倍以上の熱を伝える性質があり、水に入っているだけで陸上よりも多くのエネルギーを放出します。これが水中運動はカロリー消費が大きいと言われるゆえんです。
○水中運動の効果
・全身運動
水中で運動することにより、左右対称の動作を繰り返し、全身で運動し鍛えることが出来ます。
・有酸素運動
水中運動は有酸素運動になり、有酸素運動の効果により心肺機能向上・脂肪燃焼が見込めます。
・水圧
水圧が心肺機能をサポートすることで呼吸筋が鍛えられます。
水圧がかかることで心拍数が陸上よりも1分間あたり10拍少なくなります。
水圧により、静脈のポンプ作用がサポートされ、むくみを改善する効果が見込めます。
・体温調節機能
水中では多くのエネルギーを放出するため、血管収縮・拡張機能が高まり、体温調節機能が向上します。
・運動強度
水の抵抗を利用することで、動きを大きくしたり、速くすることで運動強度がアップします。
・負担軽減
浮力により、体重は陸上の1/6になります。それにより足腰の負担が少なく下肢を鍛えることができ、足への衝撃が大きい運動もすることが可能です。
水中運動は水の特性などにより、体にかかる負担を減らし、良い効果を与えます。暑さを和らげながら脂肪燃焼とリフレッシュを兼ねて行うのはいかがですか?ただし、水に浸かって冷えるだけでは本末転倒!効果はありません。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.25更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
今年もやってきました祭りの季節!
さいたま市日進駅前も8月6~7日に日進七夕まつりが行われます。
駅前や駅の中には七夕まつりの飾りが出ています。
今年はどのくらい七夕飾りが出るか楽しみですね!
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。


投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.24更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
7月24日は土用の丑の日ですね。先日は土用の丑といえばうなぎ!に代表される『う』のつく食べ物を紹介しましたが、土用の行事食はまだあるのをご存知でしょうか?
○いろいろある土用○○!
・土用餅
土用餅とは、土用に食べるあんころ餅のことを言います。土用餅を食べるという風習は江戸時代から小豆餡のあんころ餅になり、関西や北陸地方(特に京都や金沢)を中心に残っているそうです。
お餅は力餅、小豆は厄除けに通じるため、土用餅を食べると暑さに負けず無病息災で過ごせると言われています。
小豆に含まれているビタミンB1は糖質をエネルギーに変える作用があり、筋肉内に糖質が蓄積して疲労物質になることを防いでくれる働きがあるので、疲労回復、肩こり、筋肉痛、だるさ、夏バテなどに効果があるとされています。
・土用しじみ
しじみには夏と冬に旬があり、冬の方は寒しじみ、夏の方を土用しじみと言います。旬の時期のしじみは、栄養価が普段より高くなります。しじみは昔から「土用の蜆は腹の薬」と言われていて、「う」のつく食べ物が定着する前から、土用の食べ物でした。
しじみには良質のたんぱく質やグリコーゲンにタウリン(アミノ酸の1つ)、ビタミンが豊富に含まれています。他の貝と比較しても、含まれている栄養素は群を抜いています。しじみは、「生きた肝臓薬」とも言われるほど、肝臓の機能を修復したり、活性化する効果に富んでいます。それに加えて、貧血の予防や疲れ眼の改善、利尿の促進や免疫力の強化など様々な効果があげられます。
・土用卵
土用卵とは、土用の時期に産み落とされた卵のことをいいます。卵は栄養価が高いため、うなぎと同じように精がつく食べ物とされ、土用に卵を食べるようになりました。
たんぱく質やカルシウム、鉄分のほか、人の体内では生成できない8種類の必須アミノ酸など、ビタミンCを除くほとんどの栄養素が含まれます。特に、たんぱく質はとても良質なもので、たんぱく質の栄養価を示す基準では、もっとも優れた食品とされています。良質なたんぱく質は、胃腸の冷えを癒し体の中から暖めて免疫力を高めてくれますし、必須アミノ酸は肝機能の向上に効果があります。
土用の丑の日にうなぎとともに、しじみの味噌汁にしたり、出し巻き卵を追加したりして、相乗効果を狙ってみるのもいいかもしれません。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.23更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
今年の土用の丑の日は7月24日と8月5日です。土用の丑といえばうなぎ!という方が多いですよね。でも、土用はうなぎだけではないんです。
○土用とは?
土用とは立春・立夏・立秋・立冬の前およそ18日間をさし、雑節の1つです。本来は年に4回あるのですが、現在は夏の土用をさすことが多くなりました。土用の丑の日は、土用の間にめぐってくる丑の日をさし、年によっては2回めぐってきます。今年はその2回めぐってくる年です。
○土用に食い養生
夏の土用(7月20日頃~8月6日頃)は、二十四節気の大暑と重なり、非常に暑い季節です。そこで、厳しい暑さを乗り切るために体に良い物を食べる食い養生の風習がうまれました。
○土用の食べ物、『う』のつくもの
土用の丑の日にちなんで『う』のつくものを食べて精をつけ、無病息災を祈願します。
・うなぎ
土用の丑の代名詞ともいえるうなぎ。タンパク質、ビタミンなどをたっぷり含み、栄養豊富で精がつきます。万葉集にも夏に負けないようにとうなぎを勧める歌があるそうです。土用の丑の日にうなぎを食べると諸病にかからないという言い伝えを広めたのは、江戸時代の平賀源内だと言われています。
・梅干し
クエン酸が疲労をとり、食欲増進効果があるため夏バテ防止に効果的です。6月に漬け込んだ梅は、土用に天日干しされ梅干しとなります。また、夜露にあてる三日三晩の土用干しという方法もあるそうですよ。
・うり
胡瓜(きゅうり)・西瓜(すいか)・冬瓜(とうがん)・苦瓜(にがうり)・南瓜(かぼちゃ)などの瓜類。瓜類は夏が旬で栄養価が高く、体の熱をとったり、利尿作用があり、バランスを整える効果があります。夏の体に適した食材なんです。
・うどん
いっけん関係なさそうなうどんですが、さっぱりとして食べやすいため、暑い中でも食が進むので、土用の丑の日の食べ物と言われています。
今年の暑い夏は始まったばかりです。24日は『う』のつくもので夏を乗り切る体をつくりましょう!
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.22更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
梅雨が明け、夏も本番となりました。この時期の運動は汗をかきやすく、ベタベタ感や脱水・熱中症のリスクも高まるので、運動することが億劫に感じる人もいるでしょう。今回は夏の運動で気をつけたいこと、快適に行うためのポイントをまとめてみました。
○日焼け対策を!
日焼けによる皮膚の炎症は、ほてったりヒリヒリした痛みを伴い、ひどいと水ぶくれなどが起こることもあります。簡単にいうと火傷と同じ状態だと思ってもらえればいいでしょう。
対策としては、日焼け止めを使用したり、皮膚の露出をなるべく減らすことです。この時期帽子など頭を保護する意味でもかぶるといいでしょう。直射日光による頭痛や体調を崩す日射病(熱中症の分類の1つ)の予防にも効果的です。そして、忘れられがちなのが首周りです。首の後ろ側を無防備に日焼けさせないことも大事です。服装は通気性の良い運動しやすいもので、薄手の長袖やアーム・レッグカバーで直射日光を防ぎ、日焼けによる疲労を軽減するといいでしょう。またサングラスなどで紫外線から目を守りましょう。目の充血、炎症、緑内障、白内障の予防にもなります。
○水ぶくれはそのままで
日焼け対策をしても日焼けしてしまうことはありますよね?皮膚が熱を持ってたり、ほてって痛みがある場合はビニール袋などで氷のうを作り冷やしましょう。その際は凍傷に気をつけて下さい。
また、日焼けがひどいと水ぶくれが出来ることがあります。水ぶくれが出来てしまったらつぶさないようにしましょう。つぶしてしまうとそこからばい菌が入り、さらに悪化してしまうことがあります。
皮膚の痛みがおさまらなかったり、体全体が熱を帯びてる場合はすみやかに皮膚科を受診してください。
○運動する場所を考えよう
暑い中運動するのであれば、日陰のようななるべく直射日光のあたらない場所が望ましいです。ただし室内で風通しが悪く、熱がこもりやすい場所では熱中症のリスクが高くなります。室内でも熱中症対策はしっかりとりましょう。空調は冷風を直接体にあてないようにし、外気温との差を5℃前後に保つように調節してください。また、アスファルト舗装は日光の熱が反射し、体の上下から熱気を受けるのでかなり暑さを感じます。土の上が理想的ですが、打ち水などで体感温度を下げるのも理想的です。
○運動で気分をリフレッシュ
運動をすると体温が上昇するため、体は体温を下げようと汗をかきます。しかし体を動かして汗をかくことは、心身共にリフレッシュし気分転換をはかる効果があるといわれています。適度に体を動かして汗をかき、運動後にはお風呂で汗を流しリフレッシュするのも暑い夏を乗り切る方法の1つです。
暑さ・熱中症対策はもちろん、日焼け対策や環境面に配慮することで夏の運動も快適になります。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.21更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
そろそろ梅雨明けするんではないかと言われていますが、梅雨が明ければ夏本番ですね。暑さが増して冷房の効いた部屋で過ごす時間が多くなりますよね。涼しい場所を選んで過ごすことは、熱中症対策としては効果的です。しかし、外気温と差が激しいと体温調節機能が上手く働かず、体が冷えすぎてしまうことも。
○男女で感じ方が違う
一般的に女性は男性に比べて体脂肪が多く、筋肉量は少ないと言われています。体脂肪の性質として、熱を通しにくく一度冷えてしまうと温まりにくので、女性は冷房に対してより敏感に冷えを感じやすい傾向があります。男性は女性に比べて筋肉量が多く基礎代謝が高く、体内で熱を産生しやすく、血液循環がよくなりやすいので体が温まりやすい特徴があります。
いつもクーラーなどの冷房で体の冷えを感じる方は、筋肉量を増やす、つまり運動を行うことも対策の1つになるんです。
○下半身を使おう
運動量が減ったり、長時間の座位などで下半身のむくみや冷えを感じませんか?これは血液循環や筋肉のポンプ作用が上手く働かず、重力の影響を受け、下半身に水分が溜まりやすくなり、むくんだり冷えを感じたりしやすくなります。体が冷えると感じやすい方は、下半身を中心としたエクササイズを行ってみて下さい。日常生活の中にエクササイズえお取り入れるように階段を使うようにするのがいいですよ。
○体を温める生活習慣を
運動で体を温めるのはもちろんですが、入浴をシャワーで済ませていませんか?季節的に暑く避けられがちですが、湯船に浸かって全身を温めるのも効果的です。また、食事でも適度に香辛料の効いたものや温かい汁物を取り入れて下さい。そして、この季節大事になる水分補給では、冷たいものを飲み過ぎると胃腸を冷やしてしまうので気をつけて下さいね!
暑い季節だからこそ体を冷やさない生活が体調を整えることにつながります。
大宮・日進で丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.18更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
中医学では太っている人と痩せている人を肥人多痰(ひじんたたん)、痩人多火(そうじんたか)という言い方をします。今回はその特徴を紹介します。
○太りやすい人=肥人多痰のセルフチェック
「肥人」はからだが肥満している人を指しています。肥満している人は陽気不足の場合が多く、水を代謝することができなくなります。この水が体内に長く停滞すると痰を形成していくことから「肥人多痰」と表現されています。
「痰」は老廃物や脂肪を指す場合もありますが、もとの原因になっているものは、おもに余分な水分です。水分代謝が悪くなると、気や血の流れも悪くなり、代謝異常が起こることで体内に老廃物が溜まるのをイメージしてください。
中医学で「痰」が発生するのは「脾」という機能と関係しており、消化機能全般に弱ると出やすくなります。
・ カラダが重だるい
・ 皮膚に弾力がない
・ むくみやすい
・ 痰やおりものが多い
・ 甘いものが好き
・ 口の中が粘っこい
・ いつも眠い
・ めまいや頭痛がする
○やせやすい人=痩人多火のセルフチェック
「痩人」はからだが痩せている人を指しています。痩せている人は陰血不足の場合が多く、ラジエーターの水が減ってオーバーヒートしたように熱の症候が現れてきます。このことから「痩人多火」と表現されています。
中医学で「火」というのは、体の機能を促進する陽の気のことです。痩せている人は、臓腑の活動が活発なタイプに多く、まさに「火」なんです。太った人もこのように熱っぽく、汗っかきで怒りっぽいのでは?と思う方がいますが、「痩人多火」タイプというのは、カラダに必要な水分が不足しているのがおもな原因なのです。
中医学では体を温める陽と体を潤す陰の二つの要素があると考えるのですが、この陰分が不足し、体を冷やす水分が少ないためにほてったり、のどが渇くという症状が起こるのです。体の機能が亢進し、常に消耗しているイメージですをしてください。
・ ほてりやのぼせがある
・ 汗をよくかく(寝汗がひどい)
・ のどが渇きやすい
・ 怒りっぽく、イライラしやすい
・ 貧血気味
・ めまいや動悸がする
・ なかなか眠れない
・ 便が乾燥している
肥人多痰の方は消化の良いもの、芋類、豆類を食べるようにするのがおすすめです。体を冷やす食材は避けましょう。
痩人多火の方は体を潤す長芋や、豚肉、鴨肉、貝類、トマト、レタスなど必要な水分を補ったり、クールダウンさせる食材を摂るのをおすすめします。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.17更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
夏に注意が必要な病気といえば大半の方が熱中症を上げると思います。しかし、脳梗塞や心筋梗塞も夏場にも多く発症するんです。
○脱水が原因で発症することも
脳梗塞や心筋梗塞というと、冬の寒い時期に血管が収縮して起こる病気だと思われています。確かに寒い時期に多く、気温が上がると発症率は減っていきます。しかし、気温が31℃から32℃を超えると発症率は増えるんです。では、なぜ増えるのでしょう?それは脳梗塞や心筋梗塞を発症させる最大のリスク要因の中に「体内の水分不足」にあるからなんです。
先日お伝えしたように私たちの体は、成人で60%、新生児で80%が体液でできています。大量に発汗し、排出される水分量が増えたり、水分摂取不足により体内の水分が減ると脱水という症状が現れます。体内の水分が減ると、血液濃度が濃くなります。また、気温が高くなると体内の熱を発散しようと血管が拡張することで、血圧が低下しさらに血液循環が悪くなり、血栓ができます。それにより血栓が血管を塞ぎ、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こしやすくなります。夏の暑さは心拍数を上昇させるため、普段から不整脈がある方は注意が必要です。
○高齢者は脱水症状に気付きにくい
体は年齢を重ねると体内水分量の比率が徐々に減っていき、高齢者では50%になると言われています。成人時より10%も少なくなるんです。また、のどの渇きを感じる口渇中枢の働きが鈍くなっているので乾きを感じにくくなる傾向にあります。さらに、腎機能が低下しているため、水分調整機能が低下している方も多くいます。そして、普段から水分摂取量自体が少ないにも関わらず、トイレが近くなるからなどで水分摂取を控える方も多く、これらの要因が重なることで脱水症状になりやすくなっています。
○気をつけたい水分補給
脱水の危険性、水分補給の大切さは皆さんも理解していると思います。脳梗塞や心筋梗塞を防ぐために気をつけいただきたい水分補給のタイミングは睡眠前後です。トイレで目が覚めるからと避ける方もいますが、大人の場合コップ1杯~1.5杯の汗をかくと言われています。熱帯夜ならばもっとかいているはずです。睡眠中は血圧が低めで、血流も緩やかなため血栓ができやすく、起床時は血圧が上がり始め、血液が固まりやすい傾向があります。その負担を和らげるため睡眠前後にコップ1杯の水分を摂ることをおすすめします。
アルコールは利尿作用があるので脱水症状を引き起こしやすくなるので注意してくださいね。飲酒後は十分な水分補給をしてくださいね。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.16更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
暑い季節、エアコンで冷房病になりやすいので注意が必要です。冷え過ぎを防ぎ、健康的に夏を乗り切るために除湿機能を活用しましょう。
○体が冷えやすいのは冬より夏!
人を含めた哺乳類は、消費する熱量(基礎代謝量)の80%を体温維持に使っています。体温維持に使う熱量は、気温が高い方が少なくて済むんです。日本のように四季がある自然環境では、季節に応じて体温維持の設定が変わっているんです。言い方を変えると体温維持に使う熱量は夏になると減るということです。つまり、暑い夏の方が体は冷えやすく、一度冷えると暖まりにくい体質になるんです。基礎代謝の減り方には個人差があるのですが、基礎代謝の減少量が多い人は夏に太りやすく、冷房病になりやすくなる可能性があります。エアコンで体を冷やすのは体に悪いと言うのは本当なのです。
○空調には除湿機能が大事!
夏に外から室内に入った際涼しいと感じるのは25℃以下(23℃程度)とされています。しかし、25℃以下の室内に長時間いると手足の冷えを感じる冷房病になる恐れがあります。室内をただ冷やせばいいのではなく、重要なのは湿度を下げ、快適な空間を作ることなんです。
人の体温調節、体温上昇を防ぐには発汗が重要です。しかし、発汗しても汗が蒸発しないと体温は下がらないのです。この汗の蒸発と関係が深いのが湿度なんです。湿度には空気中の水分量そのものを示す絶対湿度と通常使用している相対湿度があります。除湿をしないでしないで温度だけ下げると絶対湿度は変化しないので相対湿度(湿度)は増加してしまいます。相対湿度が増えると発汗による体温調節が落ちてしまうんです。これも熱中症の原因の一つになるんです。
適度に除湿をしながら温度を下げることが体温調節も維持され、冷房病も避けることが出来ます。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.07.15更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
内臓脂肪を原因とするメタボリックシンドロームが浸透するようになり、肥満が注目されるようになりました。摂取カロリーが消費カロリーを上回り、体脂肪が過剰になる状態が肥満です。評価をする方法にBMIがあり、(体重【㎏】÷身長【ⅿ】2)で25以上が肥満と判定されます。
○日常生活から考えられる原因
・エネルギーをため込む食生活
乱れた食生活により摂取カロリーが消費カロリーを上回り、貯蔵されてしまう。
・エネルギーを消費できない(運動不足)
車やエスカレーターなどの移動手段や、インターネットで買い物を済ませたりなど、体を動かすために使うエネルギーが少なくなり、摂取カロリーが消費カロリーを上回り肥満につながります。
○肥満の種類
・過剰になると怖い体脂肪が蓄積した肥満
全身いたるところに蓄積する体脂肪。内臓脂肪に比べ軽視されがちですが、過剰になると糖尿病、高血圧症、脂質異常症など生活習慣病のリスクを高めます。
・生活習慣病のリスクが高い上半身肥満
腹部から上に脂肪が溜まり、体型の様子からリンゴ型肥満と呼ばれ、生活習慣病のリスクが高くなります。反対に腰から下の下半身に脂肪が溜まるものもあり、洋ナシ型肥満といい、中高年の女性に多いです。こちらは生活習慣病のリスクは少ないとされています。
・生活習慣病のリスクが最も高い内臓肥満
上半身肥満は、主に皮膚の下に脂肪が溜まる皮下脂肪と、胃や腸など内臓周りに脂肪が溜まる内臓脂肪に分けられます。内臓脂肪の方が生活習慣病のリスクを高めると問題視されています。見た目やBMIだけでは判断しにくく、かくれ肥満とも呼ばれます。
・疾患にともなう肥満
内分泌疾患(甲状腺機能低下症など)、遺伝(プラダー・ウィリー症候群など)によるものがあります。また、薬の副作用によるものもあります。
○日常生活でできる予防法・対処法
・ストレス対策をする
ストレスは食べ過ぎの原因になります。
・食べ方に注意する
食べ過ぎに注意しましょう。また、ながら食い、早食い、まとめ食い、夜食、食事を抜くなどは肥満になりやすい原因と言われています。
・飲酒や喫煙を控える
つまみの方が問題視されやすいですが、アルコール自体も高カロリーです。アルコールは肝臓内で脂肪がつきやすく、脂肪肝になりやすいです。
・脂肪のつきにくい体をつくる
脂肪を燃やし、持久力をつける有酸素運動や全身の血行を良くするストレッチなどを習慣化させましょう。
・適切なカロリーを知ろう
一般的な成人の摂取目安は1800㎉~2200㎉前後です。これを超えないようにコントロールしましょう。自分がどのくらい摂取しているかを確認するのもできるといいです。
・毎日体重計に乗る
ウエイトコントロールで一番怖いのがリバウンドです。防ぐためには日々の運動も必要ですが、自分の状態を数値化して記録しておくといいでしょう。
・病院で健診や診察を受けましょう。
○あなたの生活習慣は肥満しやすいタイプ?肥満セルフチェック
Q01 毎日の食事時間が不規則。
Q02 夕食が遅い時間になることが多い。
Q03 ついつい早食いしてしまう。
Q04 同じようなメニューばかり選んでしまう。
Q05 お酒を飲む機会が多い。
Q06 運動不足だ。
Q07 ストレスが溜まっている。
Q08 いつも手の届くところに、食べ物がある。
Q09 清涼飲料水をよく飲む。
Q10 お菓子を食べ出したら、最後まで食べてしまう。
当てはまるものが多ければ多いほど肥満のリスクが高くなります。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院