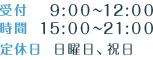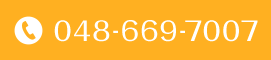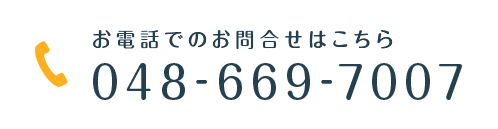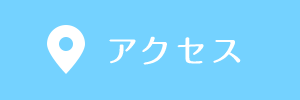2015.09.30更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
普段何気なく生活していると、自分の体が硬くなっていることに気付きにくいですよね。しかし、体の硬さを放置していると、様々な健康への影響が...
○体が硬いことで起こる問題とは
体の硬さ≒体の動かせる範囲が狭い状態と言えます。意識していなくても動作は小さくなり、筋肉のこわばりから血行不良・代謝低下を起こす可能性があります。
・痩せにくい
身体が硬いと運動効率も悪くなり、太りやすい体質に導いてしまいます。身体の硬さによってもたらされた血行不良・代謝低下は、筋肉をさらに硬くし、伸びにくくします。そのため動きにくい状態となり、運動効率が低いから太りやすくなるという悪循環が起きるのです。
体が硬いor柔らかいには持って生まれた先天的な要素もありますが、毎日のストレッチ習慣で、誰でも少しずつ体を柔らかくすることが可能です。
・腰痛になりやすい
体の柔軟性が低下すると様々な筋肉の硬さにつながります。その1つに側腹部があり、ここが凝り固まると、腰を支える力が低下してしまい、腰痛を引き起こす要因の一つとなるのです。
・精神的ストレスがたまりやすい
実は、筋肉が硬くなる最大の要因はストレスだと言われています。身体的ストレス、心理的ストレスのどちらも筋肉を硬くする要因になります。また、その逆で凝り固まった筋肉をほぐすことで、リラックス効果があるとされています。筋肉が硬いままだと、精神的にもストレスをためこむことになることも。
○柔らかい体で得られるメリット
・筋肉や関節が伸びやすく可動域が大きくなり、体も大きく動かせる
⇒消費カロリーがアップする
・体がスムーズに動くので運動することが苦ではない
⇒運動が継続&習慣化しやすい
・普段動かさないような体の隅々の筋肉まで使える
⇒脂肪が付きにくくなるうえ、身のこなしも美しくなる
・基礎代謝が上がり、血行が改善される
・疲労回復効果がある
・肩こり、腰痛改善効果
・運動時のケガ予防
・心身の老化予防
体を柔らかくすることに損はないですよね。まずは柔軟性を確認してみて下さい。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.26更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
今年の中秋の名月・十五夜(旧暦8月15日)は、9月27日(日)です。十五夜といえば月見団子やススキが思い浮かびますが、なぜお供え物をするのでしょう?
○なぜ月見にお供え物をする?
お月見にお供え物をするのは、月が風雅の対象だけでなく、信仰対象でもあったからだと言われています。十五夜をはじめとする3月見は、収穫に感謝するお祭りで、収穫物を月にお供えするようになったそうです。
○月見団子の数に決まりは?
お月見と言えば月見団子が思い浮かぶと思います。穀物の収穫に感謝し、米を粉にして丸めて作ったのが月見団子のはじまりです。十五夜は里芋の収穫を祝う行事であったため、里芋に見立てた形で、餡は月にかかった雲やきぬかつぎの皮を表しているそうです。
供える数には2つの説があります。
・満月の数⇒12個:その年に出た満月の数を供える。閏年は13個
・十五夜 ⇒15個:十五夜だから15個(十三夜は13個) 並べ方は下から9・4・2個
昔は月の満ち欠けによって暦が作られ、農作業も進められており、満月の数や、新月から何日目の月か(○○夜)ということは大きな意味があり、それが団子の数になったそうです。
○ススキはなぜ?
ススキは神様の依り代と考えられており、稲穂が実る前なので、稲穂に見立てたススキが選ばれたそうです。また、ススキの鋭い切り口が魔除けになるとも言われています。
○十五夜ばかりが月見ではない
お月見と言えば定番なのは十五夜ですが、他にも十三夜や十日夜の月見行事があるんです。
・十五夜:この頃収穫した農作物を供えます。中秋の名月とも言われ別名は芋名月。 今年は9月27日
・十三夜:無事収穫した粟や豆を供えます。別名は粟名月や豆名月。 今年は10月25日
十三夜は十五夜に次いで美しい月だと言われています。十五夜または十三夜のどちらか一方しか見ないことを片見月や片月見と呼び、縁起が悪いこととされていたそうです。
・十日夜:とおかんやと呼び、東日本を中心に行われる収穫祭です。かかしにお供え物をしてお月見をするそうです。かかしは田んぼの神様で、稲刈りが終わり、神様が帰る日になるそうです。こちらはお月見がメインではありません。 今年は11月21日
この3日間が晴れてお月見ができると縁起がいいとされています。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.24更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
多くの人が抱える疲労の問題。たくさんの疲労回復の情報もありますが、どれが正しいのかわかりにくいですよね。休んだ方がいいのか、動いた方がいいのかなど、対策方法は体のどこが疲労しているかで変わってくるんです。
○疲労は体からの警告
日々の活動で体に負担がかかっている時は、それに対して体を正常に保とうとするシステムが働くことで負担を軽減しています。疲労はそのシステムが作動しにくくなり、作業効率が低下したときに起こります。疲労は体からの警告の1つなので、本来は無視していいものではありません。
○疲労を無視すると?
体を使うということは、供給する酸素とエネルギーを消費するということです。際限なく使い続ければ、最終的にはエネルギーが不足し、細胞内で餓死状態が生じてしまいます。また、細胞が働くためには老廃物の排出も必要です。これも細胞を痛める原因となります。つまり、疲労感としての体の警告は、このままだと細胞が死んでしまい、しいては全体が危なくなるので「休め」ということです。
○疲労はどこで感じる?
疲労感は、主に脳で感じる場合と脳以外(特に筋肉)の体で感じる場合があります。
・脳で感じる疲労:脳内のセロトニンという物質が関わっていたり、作業の複雑化、記憶の連続等で脳の調整能力が低下することで起こると言われています。
・筋肉で感じる疲労:筋肉がエネルギーを消費し、老廃物が発生した結果起こります。この老廃物の1つが疲労物質と呼ばれています。
適切な疲労回復のためには、この2つの疲労に合わせた対策が必要なのです。
○2つの疲労に合わせた回復方法
・エネルギー不足に対して
体の場合は休息、脳の場合は睡眠が必要です。これらは消費されるエネルギーを減らすことになります。特に、ノンレム睡眠と呼ばれる睡眠が脳の休息には効果的です。また、エネルギーの源は食事になるので、規則正しいバランスの良い食事が大事です。
・老廃物に対して
休息することで老廃物が作られるのは減り、何よりの疲労回復になります。しかし、ゴロゴロするのだけが休息ではありません。筋肉は第二の心臓とも言われるほど、血液を流す役割をもっています。体の主な臓器はすべて血液から栄養と酸素を得ているため、積極的に筋肉を動かし血行をよくすることで、老廃物の減少を促すことができるのです。つまり、体を動かすことで筋肉を動かし、疲労物質を体から減らしていきます。普段から体を動かすと、代謝も良くなり、老廃物も少なくなります。これをアクティブレストと言います。
アクティブレストについてはこちら⇒
アクティブレストが疲労回復のポイント!
疲労回復法は、言うのは簡単なのですが、継続して行うのは大変なのです。規則正しいバランスの良い食事・嗜好品の量・継続的な運動・良い睡眠を心がけ、適度に体を動かし休息することが必要です。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.19更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
身近な食材である卵。ヒヨコが育つのに必要な栄養素が詰まっていて『完全栄養食品』とも言われるくらい栄養価の高い食材なんです。しかし、昔からコレステロールが高いので1日1個にしないと体に悪いと言われていましたがそれは本当なのでしょうか?
○卵は完全栄養食品!
卵は食物繊維・ビタミンC以外の栄養素をすべて含んでいます。そのため『完全栄養食品』とも言われています。特徴として、アミノ酸・ビタミン、ミネラルがバランス良く含まれているんです。また、ヒトの体内で合成できない8つの必須アミノ酸をバランス良く(アミノ酸スコア100)含んでいるため、良質のタンパク質源としても注目されているんです。
卵黄に多くの栄養が含まれており、カルシウムや鉄分などのミネラル、ビタミンA・B2・B12・Dなどビタミン類も豊富です。加熱するとビタミンB群が若干減少しますが、基本的には栄養価の大きな変化はありません。
○栄養価以外もある!卵の健康効果
卵は高い栄養価だけでなく、健康効果も注目されています。
卵白に含まれるリゾチームという酵素には殺菌作用があり、メチオニンという必須アミノ酸には抗酸化作用による老化防止・デトックス作用があります。最も注目されているのがコリンという物質で、脳の活性化、中性脂肪やコレステロール量の調節、血圧降下、新陳代謝促進などがあり、アルツハイマーや生活習慣病の予防効果が期待されています。
○卵にまつわるウソ・ホント
・卵はコレステロールが高いので1日1個
これは昔からよく言われていますが、実はウソなんです。健康体であれば何個食べても大丈夫ですが、食事制限が必要な人は注意して下さい。
・卵は冷蔵保存?
卵は常温で保存可能です。記載されている賞味期限は常温保存で生食しても問題ないとされる期間です。冷蔵保存であれば最近増殖が抑制されるので、長期保存も可能だとか。保存時は丸い方を上にしましょう。
・黄身の色が濃い方が栄養価が高い
黄身の色はエサに由来しています。濃淡が栄養価に関わっている訳ではありません。
卵は食べるだけでアンチエイジングになる食材です。1日1個は食べるようにし、日頃の栄養補給に役立てましょう。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.18更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
暑い夏が終わり、秋を感じる季節になりました。夏バテの様な不調が出ていませんか?もしかしたらそれは「秋バテ」かもしれないですよ。
○秋バテって?
秋は気温が安定せず、1日の中でも朝晩の気温差が大きく出ます。この気温差により自律神経が不調になり、様々な症状を起こすものを言います。気温差以外にも秋雨前線や台風での気圧変動でも自律神経のバランスが崩れることがあります。
○夏バテとの違いは?
夏バテも室内外の気温差で自律神経のバランスが崩れることで起こります。多くは熱帯夜による寝不足や、高温多湿による体温調節機能低下などによります。
秋バテは毎日または1日の寒暖差が大きく、気圧変動や夏の意識のまま冷たい物を食べ過ぎたり、夏の冷房で体を冷やし過ぎたりなどが原因になります。
○秋バテになっていませんか?セルフチェック!
・食欲がない
・胃がもたれた感じがする
・疲れやすい
・体がだるい
・立ちくらみがある
・めまいがある
・頭がボーっとする、頭が重たい、頭が痛い
・なかなか寝られない
・朝が起きられない
・肩こりがひどい
以上の症状が1~2週間以上続く時に、2個以上あれば、秋バテの可能性があり、3個以上で秋バテ、5個以上あれば、早めに対策をすべき秋バテです。
○秋バテ対策
・食事
1日3食バランスよくとる。冷たい物をさ避け、温かい物をとり、胃腸を整えましょう。
・入浴
体が冷えることで秋バテを起こしやすくなるので、腹部を温めるようにしっかり入浴をしましょう。
・運動
適度な運動により、発汗機能を高めることができます。また、血行をよくすることで疲労物質を代謝させることが出来ます。
・十分な睡眠
秋バテの症状で眠れない、起きられないという症状があります。睡眠不足になると自律神経のバランスが崩れるので、症状が悪化してしまうことになります。
・環境の変化
秋の環境の変化に体が順応しなくなります。衣類などで調節をするなどの対策が必要です。
過ごしやすい秋の季節を楽しむためにしっかり対策をしましょう。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.17更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
「活性酸素」という言葉を耳にしませんか?この活性酸素は老化や病気の原因にもなると考えられています。だんだん増えてくるといわれているのですが、活性酸素を除去する上で役立つ抗酸化作用のある栄養成分もあるんです。
○活性酸素が過剰発生する時
活性酸素は、呼吸し、食べる・歩く・眠るなど普通の生活をしていても発生します。つまり生きている限り発生し続けるのです。特に次のような時に大量発生しやすいと考えられています。
・激しい運動をした時
・細菌やウイルスに感染した時
・強い精神的ストレス状態にある、その状態が続いている時
・紫外線や排気ガスなど大気汚染にさらされている
・ダイオキシン、電磁波などの環境要因
・喫煙、肥満など
これらは逆に予防する項目にもなります。ストレスや環境汚染、化学物質を避けるようにし、禁煙や肥満予防など生活習慣の改善が予防にもつながります。
○活性酸素除去に役立つ栄養成分
・抗酸化ビタミン
人間は抗酸化ビタミンを体内で合成することが出来ません。食事からしっかり摂取する必要があります。
※ビタミンC:血液中など水分の多い場所で強い抗酸化力を持ちます。果物、緑黄色野菜に多く含まれます。
※ビタミンE:脂溶性で若返りビタミンともいわれます。酸化されやすい不飽和脂肪酸でできている細胞膜に存在し、酸化を防ぎます。ごま、うなぎ、ピーナッツに多く含まれます。
・ミネラル
タンパク質とともにミネラルの体内でつくる3つの酵素の原料になります。
※亜鉛:酸化されやすい細胞を守る働きがあります。現代人や子供は亜鉛不足になりがちなので、意識して摂取するのが望ましいです。
※セレン:活性酸素を抑制する抗酸化酵素の合成に必要なミネラルです。亜鉛と一緒に摂取するとより効果的です。イワシ丸干し、シラス干し、小麦胚芽に多く含まれます。
・フィトケミカル
主に植物に含まれる苦味、香り、色素などの成分です。
※レスベラトール:ブドウの皮などに含まれるポリフェノールです。抗酸化作用の他に、長寿遺伝子の活性化や抗糖化にも役立つのではと言われています。
※カロテノイド:緑黄色野菜などに多く含まれる色素成分。かぼちゃのβカロテンや特に抗酸化作用が強いのではといわれるトマトに含まれるリコピン、鮭に含まれるアスタキサンチン、ほうれん草に含まれるルテインなどがあります。
※カテキン:緑茶特有の渋み成分のポリフェノール。8種類あり、その総称です。ビタミンEより強い抗酸化力があるのではと言われています。
その他クロロゲン酸、サポニン、イソチオシアナートなどフィトケミカルは多彩です。
特定の成分を濃縮したサプリメントなどで偏って摂取するのではなく、様々な栄養素や成分をバランス良く食事から摂取するように心がけましょう。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.16更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
一晩寝たのに起きた時から肩が凝った感じがすることありませんか?その原因は枕かもしれません。柔らかい枕や高さがある枕が原因とも言われますが、なぜ首に負担をかけ、肩こりを誘いやすいのでしょうか?
○どんな枕が首に負担をかける?
何かしらの症状が出る時に共通しているのは、枕がフィットしていないという点にあると言われています。旅行などでいつもと違うタイプの思いますが、柔らかったり高かさがある枕で眠り、首が痛くなった経験はあるのではないでしょうか?それは枕の高さや柔らかさが、首に負担のかかる状態だった可能性があります。
○柔らかい枕はなぜ悪い?
枕で大切なのは首を支える部分があるということです。睡眠中でも大切な頭部を守るという機能は働き続けます。柔らかい枕で眠り、頭部が不安定になると、安定させるために肩や首周辺の筋肉は収縮し、力が入った状態になります。この状態は長く続かないので寝返りを打つようになり、眠りが浅くなったり、疲れもとれず、肩こり感も出るようになります。
○高い枕はなぜ悪い?
立位の姿勢が理想の寝姿勢であると聞いたことありますか?もちろん猫背はダメですよ!高さのある枕を使用すると、頭部が前傾した状態になります。この姿勢は直立にすると、頭だけを下げた姿勢になります。猫背に似た感じになりますね。
高い枕では、寝始めは首が伸ばされた感じで気持ち良さを感じますが、頭部を前傾した姿勢が続くと、呼吸が苦しくなっていきます。呼吸が苦しくなるのは睡眠時にあってはならないことですし、首や肩の筋肉が緊張し、眠りも浅く、寝返りも増え、疲労感が残ることもあります。
枕選びは、仰向けで寝た際、立位の姿勢と同じようになり、首をしっかりと支え、負担をなくすことです。全身がリラックスできるように工夫しましょう。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.15更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
布団に寝た時、朝目覚めた時など、腰や背中に痛みや違和感を感じた事はありませんか?布団やマットレスの硬さによって体にかかる負担が変わると言われています。
○睡眠中に腰が痛くなる?
枕が合わないと頭の位置が不安定で、目覚めた時に首筋に凝った感じや痛みを感じることがあります。しかし、枕だけでなく敷布団やベッドが原因になることがあります。また、首だけでなく腰や背中にも痛みが出ることがあります。
寝る際大切なことは、体の力を自然に抜くことができるかどうかです。日中体を支えている筋肉を休め、脳の疲労も回復させ、翌日スッキリt目覚めるために、心地良く感じる環境を整えることが必要です。
○布団合ってますか?体の不調チェック!
・横になった際の、首の違和感、肩周りの張り感
・なんとなく体の力が抜けない感じがする
・背中が痛む。または違和感がある
・腰が重い、痛い
・寝返りが打ちにくい。寝返ろうとすると、腰部が抜けそうな感覚になる
・お尻がマットに当たり、痛みや違和感がある
・夜中に何度も目が覚めてしまう
・適度な睡眠時間なのに、疲れがとれていない
○腰やお尻の沈み込にも気をつけて
寝る際の姿勢で、仰向けか横向きの方が多いかと思います。睡眠中は何度も寝返りも打ちます。体の向きが変わっても背中や腰、お尻などが大きく沈み込まずしっかりサポートされることが望ましいです。仰向けなら背中や腰から臀部、横向きなら肩や腰周りがどの程度沈み込むかで寝心地や安眠に影響が出るそうです。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.14更新
こんにちは!さいたま市日進駅目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
カフェインといえばコーヒーの苦み成分が有名ですが、お茶など様々な食品にも含まれています。カフェインには良い機能性もありますが、最近では過剰摂取も問題になっています。
○カフェインの機能性
カフェインはアルカロイドという窒素を含む化合物の1つです。カフェインの機能性は、眠気覚ましなど覚醒作用。疲労感抑制、鎮痛、利尿作用、胃酸分泌促進、交感神経を高めエネルギーを産生する、集中力向上、運動能力向上などがあります。
○カフェインの過剰摂取による副作用
日本でも海外でも共通の健康に悪影響の無い一日摂取許容量は設定されていません。一般的な急性作用は、中枢神経系の刺激によるめまい、心拍数増加、興奮、不安、震え、不眠症、下痢、吐き気などが起こることがあります。長期的な影響では、肝機能が低下している方は高血圧リスクが高まり、カルシウム摂取量が少ない方は骨粗しょう症、妊婦では胎児の発育阻害の可能性があります。カフェインの排出は、健康な人より腎疾患のある方、妊婦、子供はより時間がかかり、授乳中には母乳にも移行するので注意が必要です。
○カフェインの最大摂取量
様々な国や機関でカフェイン摂取量の基準が違いますが、健康な成人で400㎎、妊婦でWHOでは1日カップ3~4杯(国によっては200㎎~300㎎)未満を推奨しています。子供ではカナダ保健省が体重1㎏あたり2.5㎎としています。最近ではEUが妊婦を除く一般的成人で1日400㎎未満で、1回の摂取量は200㎎を超えないようにとされています。日本では東京都が200㎎のカフェインを食品に換算しており、コーヒー1.7杯、紅茶3.3杯、煎茶6.7杯、コーラ2ℓ4本、チョコレート6枚としています。
カフェインは健康効果もあるのですが、エナジードリンクの流行で過剰摂取の危険性も言われています。最近はカフェインゼロを謳うものもありますが、表示義務がないので知らない間に摂取していることもあります。過剰摂取には気をつけて付き合いましょう。
大宮・日進で丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院
2015.09.12更新
こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
前かがみになると腰に痛みを感じる方結構いますよね。場合によっては悪化していき、強い痛みになってしまうこともあるので早いうちに解消したいものです。
○結構多い前かがみでの腰の痛み
洗顔時や靴下を履こうと前かがみ(おじぎ姿勢)になると腰が痛む...。腰の不調で多くの方が悩んでいる症状ではないでしょうか。慢性化してしまうと毎日前かがみの姿勢で痛みを感じるため、気分もスッキリせず、動作自体がストレスになることもあります。
○腰部のコンディションチェック
腰や骨盤まわりの筋肉が硬くなり、コンディションが悪くなると、前かがみの腰痛につながる恐れがあります。次の動作でチェックしてみましょう。
1.かかとをつけ、足を軽く閉じ揃えて立ちます。
2.両手を床につけるようにゆっくりと前かがみになっていきます。この時、太ももの裏側やヒザ裏の辺りが伸びない感じがしますか?
この動作で柔軟性が低下しているように感じたり、膝裏や太ももの裏、ふくらはぎの突っ張り感でこれ以上前屈できないと感じたり、不快感・違和感が腰や足にある場合は、腰部や骨盤周りに問題がある可能性があります。ただし不快感がなくても筋肉の過度な緊張で前かがみで痛む腰痛を起こすこともあります。
○こんな前かがみの腰痛は注意が必要!
お尻から足の指先の間でしびれを感じる場合は注意が必要です。痛みやしびれの範囲、筋力低下の有無、下肢の動きなどの確認を必要とし、自己判断をおすすめできない状態のものもあります。咳やくしゃみ、トイレでお腹に力を入れることが辛い、歩行困難などがみられる時は医療機関に早めに受診しましょう。
○前かがみの腰痛予防
前かがみで痛みが出る腰痛は、腰部や骨盤周りの筋肉疲労が関係しています。腰部や骨盤周りの筋肉そのものが痛みの原因になるものもありますし、太ももやふくらはぎが原因になり、腰部や骨盤周りに負担をかけているものもあります。姿勢による負担を軽減させ、腰部や骨盤周りのバランスを安定させることが大事です。また、腰周りや下肢をストレッチなどでのケアが必要です。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。
投稿者: コンディショニングラボ南口駅前接骨院