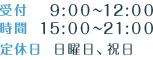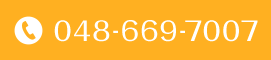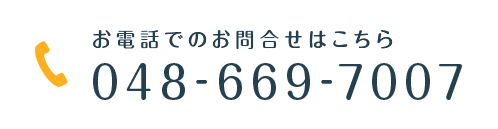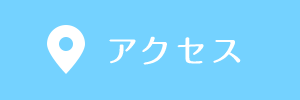こんにちは!さいたま市日進駅南口目の前30秒!
コンディショニングラボ南口駅前接骨院の神田です。
近年、「スマホ認知症」という言葉が注目を集めています。正式な医学用語ではないものの、スマートフォンの過度な使用によって、物忘れや集中力の低下といった“認知症に似た症状”が現れることから名付けられました。
〇スマホ認知症とは?
「スマホ認知症」とは、スマートフォンの使い過ぎにより脳の働きが低下し、物忘れや注意力の欠如、情報処理の遅れなど、まるで認知症のような状態になることを指します。特に若い世代にもこの傾向が広がっており、現代社会における新たな健康リスクといえるでしょう。
〇「認知症」と「スマホ認知症」には違いがあります。
「認知症」とは、情報を脳にインプットすることができなくなっていく。「海馬」と呼ばれる部分が萎縮していってしまうので、情報を取り入れることができなくなる。つまり、記憶ができない状態です。
一方で、「スマホ認知症」とは、スマートフォンを目的もなく見ていると、情報がどんどん脳に入ってきます。その膨大な情報に脳が疲れてしまうことにより、今度は情報を取り出すことができなくなってしまう。
記憶している、覚えている。しかし、その引き出しがどこにあるのかが分からない、引き出しから取り出せなくなってしまうというのが「スマホ認知症」です。
〇代表的な症状
以下のような症状に心当たりはありませんか?
・人の名前や予定をすぐ忘れてしまう
・SNSや通知が気になって集中できない
・スマホがないと不安になる(スマホ依存)
・複数の情報を処理するのが遅くなった
・寝る前までスマホを触っていて睡眠の質が悪い
これらが続くと、日常生活や仕事、学習のパフォーマンスにも悪影響を与えます。
〇なぜスマホで脳が疲れるのか?
スマートフォンは便利ですが、常に大量の情報を浴びることで、脳が休む暇をなくしています。以下のような点が脳疲労の原因になります:
・マルチタスクによる集中力の低下
・SNSや通知で頻繁に注意が分断される
・インターネット検索に依存し、自分で思い出す力が低下
・ブルーライトによる睡眠障害
〇スマホ認知症の予防・改善方法
スマホとの付き合い方を見直すことで、脳への負担を軽減できます。
・デジタル・デトックス
1日1時間、スマホを見ない時間を設ける
食事中やトイレなど「ながらスマホ」をやめる
・睡眠環境の改善
就寝1時間前はスマホを使わない
アラームは別の目覚まし時計に切り替える
・アナログ回帰
手帳に予定を書く
調べ物は辞書や本を使うよう心がける
メモをとる習慣をつける
・脳を鍛える習慣を持つ
読書やパズル、運動などで脳に刺激を与える
会話や人との交流を意識的に増やす
スマートフォンは生活を豊かにするツールですが、使い方次第で私たちの脳に大きな負担を与えてしまいます。「スマホ認知症」は誰にでも起こり得る問題です。日常生活の中でスマホとの距離を見直し、脳をしっかり休ませる時間を持つことが、心と体の健康を守る第一歩となります。
大宮・日進の丈夫な体をつくるコンディショニングラボ南口駅前接骨院でした。